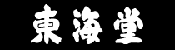AO入試体験談②
岩本 遼(総合政策学部2年)
-
出身校
高松中央高校
-
高校での成績

受験生の皆さんへ
〇SFCを受験しようと思ったきっかけ
3 月にあった全国選抜大会の後に慶應義塾大学空手部 OB の方から練習会の
お誘いを受けて、初めて練習会に参加しました。もともと文武両道ができる大
学に進学したいという思いがあり、練習会の後の説明会で初めて SFC について
の説明を聞き、練習面では、いい雰囲気の中メリハリのある練習を行っており、
勉強面では、私には充分過ぎるほど環境が整っているなと思ったので、挑戦し
てみようと決めました。
〇志望理由書テーマを決めたきっかけ、経緯
テーマで悩んでいた際に自分の副担任から農地の荒廃化の問題があると言わ
れ、そこで初めてその問題について調べていると、荒れた農地によって様々な
悪影響が生まれているのに対して解決に進んでいないという現状や、農業を行
う人が減少しているという現状を知り、自分の手でこの問題を解決しなければ
いけないと感じたからです。
〇受験において工夫したこと、大変だったことなど
まず、テーマ決めの際に自分の人生を振り返ってみたり、興味があることを
書き出してみたりして、他の受験者がなかなかスポットライトを当てないテー
マになるよう頑張りました。1 次の論文・PR 動画・自由記述書は、先輩の方々
などに何度も添削をしてもらったりアドバイスを頂いたりし、矛盾点が無いよ
うに気をつけました。インターハイが終わってからは、ほぼ練習に参加せずに
面接の対策をしました。2 次の面接は、論文のテーマについてより詳しく語れ
るようになる為に農林水産課の方にお話を伺いに行ったり、教授の本を読んだ
りして、更に知識を身につけました。
10月15日は慶應義塾空手の日
(創部および体育会承認記念日)
慶應義塾體育會空手部100周年
2024年10月15日